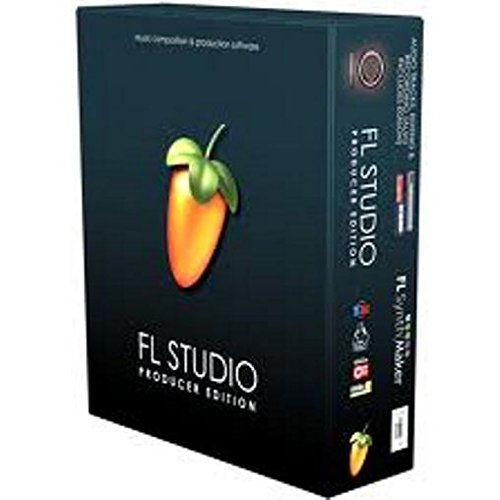前に手に入れたSonicwareのLiven 8bit warpsですが、
随分お気に入りになっていて、
改めてレビューとかしてみようかなと思い、ここに至ります。
Livenシリーズにかかわらず、どうもYoutubeのレビューとか、
各種サイトの記事とか見ても、知りたかったポイントがなかなか触れられていないのが
もどかしいんですよね。
そういう事もあって、自分なりの解釈を入れながらレビューしてみます。
まあ、まずは作っているSONICWAREさんのサイトがありますので、ご紹介を。
ja.sonicware.jp
【だいたいのイメージ】
ざっくり乱暴に言うと、
減算式シンセが乗ってる、
4trルーパーと1trシーケンサーのグルーヴボックスです。
4trルーパーといいつつそのうちの1trは外部入力専用なので、
単体機としては3trしか使えないっていう(笑)
シーケンサーはあるので4trとして使うことはもちろんできます。
このルーパーが本当に面白くて気に入っています!
【8bitについて】
さて8bitってあの音でしょって思っていると、
意外とそういう音にはなりません。
というか意図的に狙わないとそういう音にならないんですよね。
というのも、普通に音を作ると、
音量変化もフィルターも通ってしまうから普通のシンセ的な音が作れてしまっているんですよね。
【音源構成について】
結構買う前にわからなかった部分で、使ってみてわかったのですが、
シンセとしては、少し機能が簡単になっています。
OSC(Detuneあり、PitchにLFOかかる)
⇒ Amp(EGかかる)
⇒ Filter(Resonanceつき。LFOかかる)
そのうえで、このOSC部分に、Warp、Attack、Morph、FMが選べます。
Warp :2つの波形を混ぜる
Attack :2つの波形を切り替える A⇒B。
MorphのようにB⇒A⇒Bのような動きはしない。
Morph :2つもしくは3つの波形を時系列でモーフィングさせる。
FM :2OPのFM。LFOかかるので遊べる。
なお、ノイズジェネレーターはないです。
また、PitchとFilterのLFOはサイン波で共用となります。
とはいえ、パラメータロックががんがんかかるので、
あまり困んないというのはすごく強調しておきますね(笑)
【エフェクト】
エフェクトはディレイとかコーラス、フランジャー、ビットクラッシャーなどが
あります。
あと、音の出口にリバーブがついていますが、
ルーパーからリバーブに流し込めるかどうかの調整はできませんでした。
外部入力はできるみたいですが(ひょっとしたらやり方あるのかな)
ちなみにカセットシミュレーターがリバーブの中に入っていたり
(リバーブじゃないけど笑)
シーケンサーは1trです。
難しいことは、ルーパーとやりましょうという仕様です。
ステップシーケンサーなので、どうやったって勝手にクオンタイズされます。
またパラメータロックが使えるのがすごく面白くて、大体の面白いことはできます。
なお音源方式、例えばWarpをAttackやFMに変えるという事はできませんが、
その中のパラメータを変更することはできます。
【ドラムトラックについて(打ち込み編)】
実は難関なのがドラムトラックです。
ピッチにEGないし、ノイズジェネレーターもない。
音作りができなくてもう発狂しそうですよね(笑)
まあ、プリセットパターンもあるし、迂回しちゃってもよいところですが、、、。
この辺り、(多分イギリス人でSonicwareと契約してそうな)
クリスさんやSonicwareの遠藤さんがYoutubeで述べていたりするんですが、
やっぱりオリジナリティ出したいところなので、
ざっくり音作りの方法論を示しておきます。
--------------------------------------------------------------------
1.ドラムトラックを1トラックで作りこむシーケンスでは、
同時発音(例えばキックとスネア)はなしと考える。
2.基本的にはどんな音でもドラムトラックとして成り立つ。
そして、以下のような表現をしない限りドラムトラックとして成り立たない。
⇒低い音程でのスイープダウン:キック
⇒キックよりも高い音程でのスイープダウン:スネア
⇒高い音程でのスイープアップ、もしくはPitchLFOなど:ハイハット
3.基本となる音を作るか作らないかを決める。
FMで高い倍音を出しながらLFOかけて少しでも複雑な音を作るのもありだし、
パラメータロックを駆使して、各音で別の音を作るのもあり。
4.パラメータロックで、フィルターやPitchLFOなどで、音を追い込む。
--------------------------------------------------------------------
ここまで書いて思いましたが、
これ、普通の人なら脳みそ死にますね・・・という事で以下をご覧ください。
【ドラムトラックについて(リアルタイム編)】
上記のように複雑なことをしなくても、
実はプリセットパターンからオリジナルのリズムは作れるというのがここからのお話。
プリセットパターンを選びつつ、スタッターで演奏してアレンジしたものをルーパーに記録できるんです。
これすごく楽。
ちなみにこれを応用してドラムを遊んでみたりしたのが下の動画。
youtu.be
【ルーパー】
もちろんシンセをそのまま手弾きしながらルーパーに流し込んでも行けますが、
基本的にはルーパーにシーケンサーで音を流し込んでいくイメージです。
これでさらに面白いのがパターンシーケンサーのパターンを連結させることが出来て
さらにルーパーに1trずつ流し込んでいけるという、
説明しててもよくわかんないことが出来ます(笑)
例えばですが、
ドラムシーケンス⇒ベースシーケンス⇒リフシーケンス⇒メロディシーケンス
というようにパターンを連続して再生するとします。
その時に、
ドラムシーケンス⇒ルーパー1tr
ベースシーケンス⇒ルーパー2tr
リフシーケンス⇒ルーパー3tr
メロディシーケンス⇒シーケンサーで鳴ったまま
という事になるんですね。
そして実際に再生している音を聞くと、
ドラムパート
⇒ドラム+ベースパート
⇒ドラム+ベース+リフ
⇒ドラム+ベース+リフ+メロディ
となって、これ普通のリミックスじゃんみたいになります。
すごっ(心の声)
さらに外部入力つないでおけばルーパー4tr目も使えるから、
控えめに言って強すぎです。
まあ、ちょっと残念なこともあって、
ルーパーは音量、パン、ミュートしか操作できないというところもありますが、
なんとかなるでしょう。
【操作性】
癖があるとか巷で言われているところもありますが、
正直、自分には癖は感じなかったです。
ただ、Livenシリーズは機種ごとに操作性が異なっていたりするので、
そこは気にしたほうがいいかもしれません。
操作性に関連して、鍵盤にはベロシティついていないので、そこはご注意を。
でも、ベロシティはつまみで弄る仕様なので、問題なかったです。
ちなみに遊んだ動画も貼っておきますね。
youtu.be
さて、今日はここまで。
仲間増えてほしいなあという願いも込めて、興味ある人は是非ご検討くださいー!